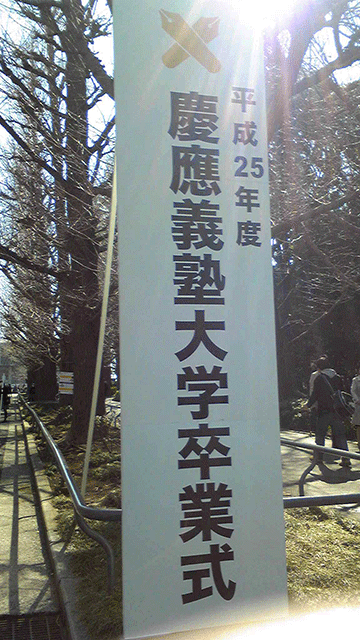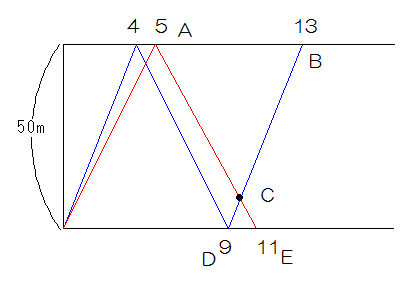別に活動報告書のためだけではないが、やはり4年生以降もなるべく習い事や塾以外の学習機会を持ち続けるべきではないだろうか、と思います。
さすがに6年生の最後の半年はまあ、受験に絞ってもいいかもしれないが、それまではやはり何とかバランスをとって、スポーツや音楽や絵画など、子どもが好きなことをやり続けることは大事だと思うのです。
子どもにはやはり複数の引き出しがあることが望ましいのです。例えば勉強があって、スポーツがあって、音楽があって、いいのです。スポーツは別にプロの選手になるだけが道ではないわけで、一生サッカーや野球を楽しんでいる人たちは多いし、またそれが観戦にもつながっていくでしょう。で、そういう興味があるものが複数あれば、それだけ自分の可能性を試せるところが増えるわけだから、1本しか掘るところがない、よりはよほど人間性に幅が出てくる。
受験勉強のために、すべてをやめてそれに没頭する、というのはやはり小学生には危険ではないでしょうか。ただでさえ、子どもが偏差値という軸に集約されやすい受験環境がすべてになってしまえば、子どもの人に対する価値観がそれだけに固まってしまう。本当はいろいろなものが上手である人間に対するリスペクトがあるべきなのに、それを失ってしまう可能性があるし、また、それは自分の可能性をも縮小してしまうことになりかねません。
だから、まあ、習い事は細くでもいいから、なるべく長く続けることを考えてはどうでしょうか。
例えば音楽にしても、やはり中学校になってその楽器を楽しめるということは、本当に素晴らしいことだと思うのですが。
=============================================================
今日の田中貴.com
そういえば
==============================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
当てる子
==============================================================

==============================================================

==============================================================
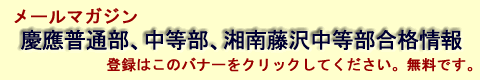
==============================================================