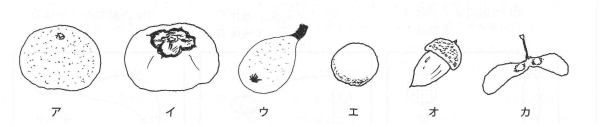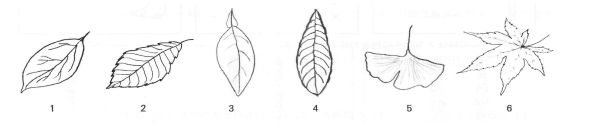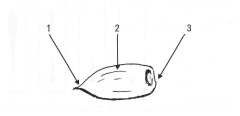中等部の理科は25分、50点満点。
大問は5問ないし6問。小問は40問程度になるので、時間は十分ではないかもしれません。物理、化学、生物、地学の4分野がそれぞれ1問ずつ。それに実験をからめた問題が出されている年が多いようです。
今年の問題も全部で大問5題。
【1】は昆虫の問題。テーマは昆虫の特徴。
カマキリ、チョウ、カブトムシ、トンボ、セミですから比較的特徴のはっきりした昆虫なので、さほど難しくはなかったのですが、それでも卵、幼虫、さなぎ、成虫と成長していく時期は不確かな子が多かったかもしれません。
【2】は食塩水を凍らせた後、半分ぐらいとけたところで、固体と液体に分ける実験。
結露に関する問題が2問。
残り3問は、半分ぐらいとけたときの固体と液体でどちらの方が食塩が多いか、ということを元に考えます。この3問は最初を間違えると全部間違えてしまう可能性があったでしょう。
水は水の分子同士が結合して凍ります。しかし、食塩水の場合は食塩が溶けて、水と水の結合を邪魔するので、凍る時は凍りにくく、水より低い温度でなければ凍りません。逆にとけるときは濃い食塩水ほど早く溶けていきます。
ここを間違うと、点数がまとまらなかったので結構難しかったと思います。
【3】はペーパークロマトグラフィーに関する実験。
論理的に実験結果を考えなければいけない問題です。知識は全く必要ないので、思考力を問われました。
【4】は植物の実の問題。
今の子どもたちがここまで葉の種類を見分けられるか、といえば甚だ難しいと言えるでしょう。
詳しくはこちらから。
【5】ふりこと物体の運動の問題
実験結果から仮説を導いて、そこから予測を立てる問題でした。
今年は全体的に理科は難しかったのではないかと思います。解答形式はすべて記号選択式です。近年社会や国語では記号式だけでない問題を出題しようという流れになっているようですが、理科は記号選択ばかりになっています。
全体的に実験、観察、観測問題が多く、その結果を問う問題が出題されているので、実験問題に対する練習は必要でした。
理科計算は決して多くありませんが、しかし、考えさせる問題が増えてきています。ただ知識を知っていれば良い、というのとだいぶ違ってきていますので、ここ数年の過去問をやってみて、出題傾向に慣れてほしいところです。
一通り知識の勉強が終わったら、他校の過去問を含め、実験と観察に関する問題は適宜練習を深めていってください。仮説の立て方、対照実験の考え方など論理的に考える力が求められてきていますので、ひとつひとつの問題をていねいに復習しながら、考え方をマスターしてほしいと思います。
=============================================================
今日の田中貴.com
溶解度の問題
==============================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
本物を見に行こう
==============================================================

==============================================================
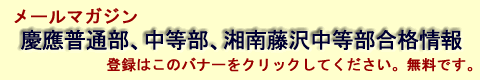
==============================================================