植物や動物の問題は慶應は少なくありませんが、しかし、やはり子どもたちにとって身近なものを考えています。例えば野菜については、過去、良く出題されてきました。
普段何気なく見ている果物や野菜も、多くの子どもたちにとっては調理された後のものしか、知らないことが多い。だから、こういう問題を出されると困ってしまうわけです。
以下は平成22年の中等部の2番
私たちは季節によっていろいろな野菜や果物を食べることができます。次の問いに答えなさい。
(1)下のあ~き は東京で出回る果物の旬の時期を示しています。あ~き にあてはまる果物をあとの選択肢からそれぞれ選び番号で答えなさい。
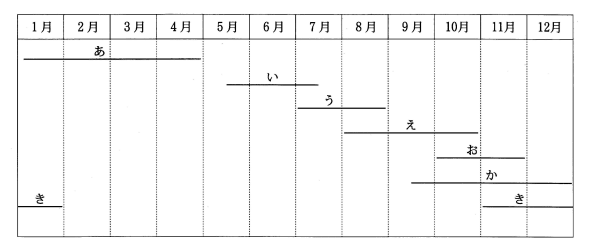
1 イチゴ 2 カキ 3 サクランボ 4 ナシ
5 ミカン 6 モモ 7 リンゴ
(2)次の野菜の主に食べるところは植物のどの部分ですか。あとの選択肢から選び番号で答えなさい。
く:オクラ け:キャベツ こ:ゴボウ さ:ジャガイモ し:タマネギ
1 根 2 葉 3 茎 4 果実 5 種子
(3)次の中からキャベツと同じ仲間の植物の組み合わせを選びなさい。
1 ゴボウとダイコン 2 ゴボウとブロッコリー
3 ゴボウとレタス 4 ダイコンとブロッコリー
5 ダイコンとレタス 6 ブロッコリーとレタス
(4)次の中からジャガイモと同じ仲間の植物の組み合わせを選びなさい。
1 カボチャとキュウリ 2 カボチャとナス
3 カボチャとピーマン 4 キュウリとナス
5 キュウリとピーマン 6 ナスとピーマン
出てきている野菜や果物はどれも食卓に上がるものばかりでしょう。これは知らないという子は少ない。しかし、季節感となると心もとなくなる。最近は1年中見られるものが多くなったから、かえって厄介かもしれません。
(3)(4)はちょっと難しいかもしれません。キャベツはアブラナ科ですから、ダイコンが花からピンとくればいいですが。ついレタスを選んでしまいそうですが、これはキク科です。
(4)ジャガイモはナス科。ピーマンもナス科です。
いずれにしても、本当に身の回りで知っている植物、動物に気を付けておくのが、中等部の生物のポイントと言えるでしょう。
(答え)
(1) あ 1 い 3 う 6 え 4 お 2 か 7 き 5
(2) く 4 け 2 こ 1 さ 3 し 2
(3) 4
(4) 6
=============================================================
今日の田中貴.com
学校選びの妙
==============================================================
中学受験で子どもと普通に幸せになる方法、本日の記事は
わかり始める子
==============================================================

==============================================================
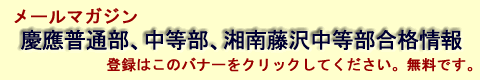
==============================================================


